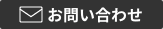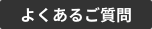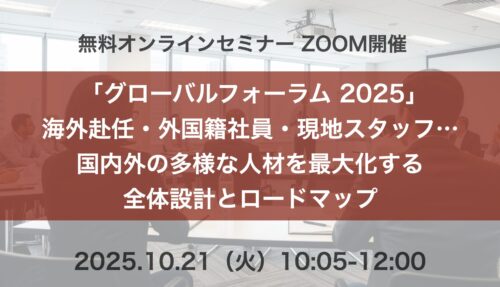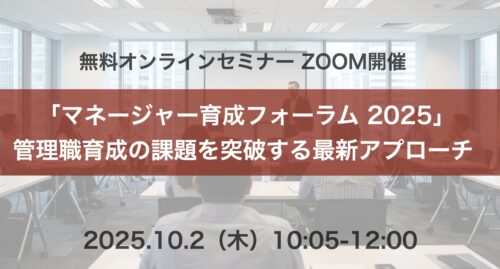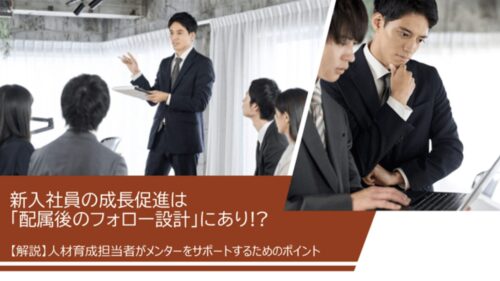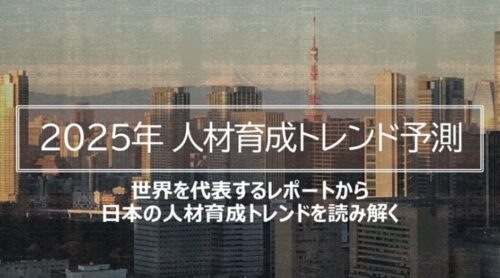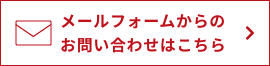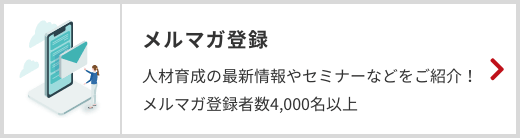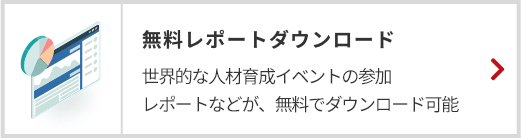人材育成の最新トレンドをブログで情報配信中
アイディア社では人材育成情報・参考事例・具体的なノウハウなどをブログやメールマガジンでお届けしております。ぜひ、御社の人材育成にお役立ていただければ幸いです。
-
2025.10.23
【セミナーレポート】グローバルフォーラム 2025
-
2025.10.07
【セミナーレポート】マネージャー育成フォーラム 2025
-
2025.08.06
【セミナーレポート】1-2-3年目 社員育成フォーラム 2025
-
2025.06.25
【セミナーレポート】ATD人材育成国際会議2025 報告会
-
2025.05.01
2025年の新入社員研修で見えた傾向と、配属後フォロー設計のポイント
-
2025.03.28
海外拠点×外国籍社員の育成「新常識」|3つのケース別・研修設計の実践ポイント
-
2025.02.28
新入社員の成長を加速する「配属後フォロー設計」4ステージと人事の打ち手
-
2025.02.20
【セミナーレポート】グローバルで活躍するためのケース別・人材育成の導入事例と最新情報「グローバルフォーラム 2025」
-
2025.01.28
2025年の人材育成トレンド予測|AI×ヒューマンスキルを「成果」に変える設計ポイント
-
2024.12.12
【セミナーレポート】導入事例(効果実証済み)から学ぶ「ラーニングイノベーションフォーラム 2024」