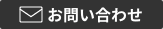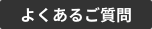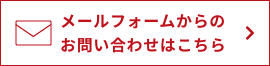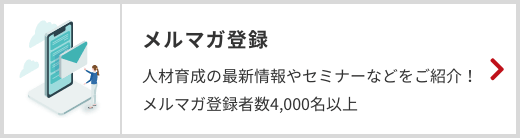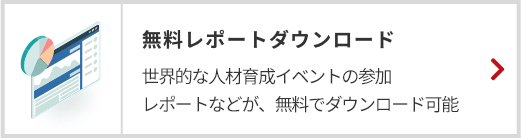研修事例のご紹介
アイディア社の研修プログラムを実施された事例のご紹介。
数多くのオリジナル研修プログラムを設計、実施してきた経験をもとに、お客様の個別ニーズに合った最適な研修を設計・実施いたします。
-
アフターコロナで変化する職場環境:若手社員の主体性と問題解決能力を高めた事例
情報・通信・ソフトウェア
-
単発研修から年次連動型の演習中心研修でスキルとマインドを定着化した事例
銀行・証券・投資・保険